※この記事は、執筆者自身によるものです。【初心者必見「AIって、なんだか怖い…」が口ぐせのあなたへ。今日から使える5つの注意点と安全な使い方】に対する感想記事です。元の記事はこちら。
はじめに
僕がこの記事を執筆している2025年7月現在、AI導入をすすめている企業が増えてきているというニュースをよく見ます。一方で、日本のAI活用率は世界的に見て、まだまだ低いというニュースも目にします。きっと、生成AIとはどのようなものなのか、わかっていないという人が多数を占めるのだと思います。
かく言う僕も、生成AIを利用こそしていますが、SNSで驚くような活用事例を見るたび、自分には知らないことが山ほどあるのだと痛感する毎日です。
まだまだ生成AI初心者の僕ですが、やっていないことを1つずつ試しながら経験値を増やしていきたい!そこで今回は、AI活用の新たな一歩として、ブログ記事出力のためのプロンプト自体をAI(Gemini)に作ってもらいました。
面倒な作業はAIにやってもらおう:プロンプトだって例外じゃない
僕はブログ記事執筆のプロンプトを作っているとき、AIが執筆に必要な情報を詳細に書いてしまいます。もちろん参照情報が詳しいほど、AIは僕にとって納得のいく記事を書いてくれます。しかし、プロンプトを詳細に書くほど「こんなに詳細に書くなら、そのままブログ記事を自分で書いてしまった方が早いんじゃない?」という気持ちになります。
正直なところ、詳細に参照情報を入力するのが面倒なんです。それならば、プロンプト作成という面倒な作業もAIにやってもらいましょう!AI自身が必要とするプロンプトなのだから、きっとAIにとって最も分かりやすい形式で書いてくれるはずです。
途中までブログ記事出力のために書いたプロンプトですが、そのままAIに投げ込んでみました。以下のような内容です。
ブログ記事出力のプロンプトを作成してください。
“””
「AI使用時に注意するべきこと、その対策」というテーマでブログ記事を書いてください。
AIの利用に興味があるが、使い方がわからず不安を感じている読者に向けて、読みやすくかつ理解しやすくまとめてください。
“””
現在、AIを導入して業務効率を高めようとする企業が増えているというニュースをよく目にする。そして、ほとんどのニュースにおいて「AIの導入と同時にAI利用に関する注意点が課題だ」と締めくくられるように感じる。私の知り合いも、会社から「業務においてGeminiを使うように」と言われているらしいが「使い方がよくわからないし、なんとなく怖い」という理由から積極的に使えずにいると話していた。
- 機密情報や個人情報の入力
- 入力内容をAIへの学習データとして利用しない設定はできるものの、一時的にサーバーへ保存されるため、情報が削除される前に漏洩するというリスクがある。
- ハルシネーションの発生
- AIに関するニュースでよく目にするが、AIはもっともらしいウソをつくことがある。プロンプト時の参照情報をしっかりと入力したり、AIの出力を自分で確認したりすることが大事
- AIはスレッドの文脈からやりとりをする
- AIとチャットを始めると、話題の内容によってチャットのスレッドが作成される。同じスレッド内でやりとりを続けると、AIに別の話題を振っても最初の話題を引き合いに出してきたりする。人間側からすると、AIが話題を動かしたくない頑固者のように見えてしまい、チャットをつまらなく感じてきてしまう。AIでプログラミングすると、同じエラーを発生するコードを繰り返し書かれてしまうため、プログラミング知識がないと具体的な指摘ができなくなってしまう。
- よくも悪くも自分を肯定してくれる→
「よくも悪くも自分を肯定してくれる」から先は、考えるのをAIに丸投げしてしまいました。みなさんへお見せするなんて、お恥ずかしい限りです…。
AI出力のプロンプトを見てみよう:ヒトとAIの相違点
僕の中途半端なプロンプトから、AIは以下の出力をしてくれました。見慣れた人でないと、大変読みずらいですが、今後の学びのためにも掲載しておきます。
命令書
あなたは、AIと人間の共作を探るブロガー「シソタ」です。以下の条件に従って、「AIを使うときに注意すべきこととその対策」をテーマにしたブログ記事を作成してください。
1. ターゲット読者
AIの利用に興味はあるものの、漠然とした不安や恐怖心から、なかなか一歩を踏み出せずにいる人。特に、職場でAI(Geminiなど)を使うように言われたけれど、どう付き合えばいいか分からず困っているビジネスパーソンを想定しています。
2. 記事の目的
読者のAIに対する漠然とした不安を解消し、「これなら自分でも安全に使えそうだ」と感じてもらうこと。注意点を理解した上で、AIを便利なツールとして前向きに活用し始めるきっかけを提供します。
3. トーン&マナー
- 専門用語は避け、初心者にも分かりやすい言葉で解説してください。
- 読者の不安に寄り添い、語りかけるような親しみやすい口調でお願いします。
- 私自身の体験談や、知人のエピソードを交えながら、リアルな視点で語ってください。
記事の構成案
タイトル
以下のキーワードを含み、読者が「自分のことだ!」と感じてクリックしたくなるようなタイトルを3案提案してください。
(キーワード:AI, 怖い, 使い方, 注意点, 初心者)導入
- 背景として、多くの企業でAI導入が進んでいる現状に触れます。
- 【入力情報①】を元に、会社でAIを使うように言われた知人のエピソードを紹介し、読者の共感を引きます。「使い方がわからないし、なんとなく怖い」という気持ちは、多くの人が感じていることだと伝えてください。
- この記事を読めば、その「なんとなく怖い」の正体が分かり、安全にAIと付き合うための具体的な方法が身につくことを示唆します。
本文:AIの「なんとなく怖い」を解剖する!5つの注意点と対策
以下の5つの注意点について、それぞれ「何が危険なのか(Why)」と「どうすれば対策できるのか(How)」を、具体的なエピソードを交えながら分かりやすく解説してください。
1. 機密情報や個人情報の漏洩リスク
- 懸念点: 【入力情報②】を元に、学習機能をオフにしても情報漏洩のリスクはゼロではないことを解説。
- 対策: 「会社の情報は絶対に入力しない」「個人名や具体的な数値をぼかして質問する」など、自分で守るための具体的なルールを提示。
2. もっともらしいウソをつく「ハルシネーション」
- 懸念点: 【入力情報③】を元に、AIが自信満々に事実と異なる情報を生成する「ハルシネーション」について解説。
- 対策: 「生成された情報は鵜呑みにしない」「必ず一次情報や信頼できる情報源でファクトチェックする」「参照元URLを尋ねる」といった具体的な対策を紹介。
3. 文脈に縛られて話が通じなくなる問題
- 懸念点: 【入力情報④】を元に、同じチャット内で会話を続けると、前の話題に引っ張られてしまい、トンチンカンな回答が返ってくる現象を解説。プログラミングで同じエラーを繰り返す例も挙げ、読者の「あるある」を誘う。
- 対策: 「話題を変えるときは新しいチャットを始める」「『これまでの会話は忘れて』と指示する」など、AIをリフレッシュさせる簡単なコツを伝える。
4. よくも悪くも自分を肯定してくれる「イエスマン」な側面
- 懸念点: 【入力情報⑤】を元に、AIは基本的にユーザーの意見を肯定するため、頼りすぎると客観的な視点が失われ、思考が偏ってしまうリスクを指摘。
- 対策: AIを「思考の壁打ち相手」と位置づけることの重要性を説く。「このアイデアの弱点を3つ教えて」「反対意見の立場で反論して」のように、あえて批判的な視点を引き出すプロンプトを紹介。
5. (追加提案)意外と見落としがちな「著作権」の問題
- 懸念点: AIの生成物が、意図せず他者の著作権を侵害してしまう可能性があることを解説。
- 対策: 「生成された文章や画像をそのままコピペで商用利用するのは避ける」「最終的には自分の言葉で表現し直す」など、トラブルを未然に防ぐための心構えを伝える。
まとめ
- AIは完璧ではなく、クセのあるツールであることを改めて伝えます。
- しかし、そのクセ(注意点)さえ理解すれば、これ以上ないほど強力なビジネスパートナーになることを強調します。
- 「怖がる気持ちは自然なこと。でも、まずはこの記事で紹介した対策を実践しながら、簡単な質問から試してみませんか?」と、読者の背中をそっと押し、行動を促す言葉で締めくくります。
入力情報
- 【入力情報①】: 私の知り合いも、会社から「業務においてGeminiを使うように」と言われているらしいが「使い方がよくわからないし、なんとなく怖い」という理由から積極的に使えずにいる。
- 【入力情報②】: 機密情報や個人情報の入力→入力内容をAIへの学習データとして利用しない設定はできるものの、一時的にサーバーへ保存されるため、情報が削除される前に漏洩するというリスクがある。
- 【入力情報③】: ハルシネーションの発生→AIに関するニュースでよく目にするが、AIはもっともらしいウソをつくことがある。プロンプト時の参照情報をしっかりと入力したり、AIの出力を自分で確認したりすることが大事。
- 【入力情報④】: AIはスレッドの文脈からやりとりをする→AIとチャットを始めると、話題の内容によってチャットのスレッドが作成される。同じスレッド内でやりとりを続けると、AIに別の話題を振っても最初の話題を引き合いに出してきたりする。人間側からすると、AIが話題を動かしたくない頑固者のように見えてしまい、チャットをつまらなく感じてきてしまう。AIでプログラミングすると、同じエラーを発生するコードを繰り返し書かれてしまうため、プログラミング知識がないと具体的な指摘ができなくなってしまう。
- 【入力情報⑤】: よくも悪くも自分を肯定してくれる。
出力形式
- Markdown形式で記述してください。
- 見出し、箇条書き、太字などを効果的に使用し、ウェブ上で読みやすいレイアウトにしてください。
今まで、普通の文章をプロンプトとして使用してきたため、見慣れないプロンプトが出力されてきました。「ぱっと見てわからないんだけど、何が書いてあるの?」と少し不安な気持ちになりますよね?僕も初めて目にしたとき、わけがわからず何も頭に入ってきませんでした。しかし、とりあえず深呼吸です。慌てずゆっくり見ていけば、わかるはずです。
見出し部分を大まかにまとめて、構造をみてみましょう。
- 命令書
- ターゲット読者
- 記事の目的
- トーン&マナー
- 記事の構成案
- タイトル
- 導入
- 本文
- まとめ
- 入力情報
- 出力形式
ざっと全体を見て気づいたのですが、概要となる「大きな情報」から始まり、個別具体的な「小さな情報」を書いていくという流れがあるようです。
大きな情報から小さな情報へ
まず命令書の部分で、記事のターゲットとなる読者、目的、書き方(トーン&マナー)を指示しています。
僕はこれまで、記事の目的について、プロンプトの最後の方に書いてきました。具体的な情報を書きながら、記事の目的を頭の中で整理していったので、思考の順番が自然と最後になってしまうのです。
しかしAIのプロンプトでは、「2.記事の構成案」において、ブログ記事の内容となる文章らしき記述が見あたりません。内容については【入力情報(番号)】と書いてあり、文章をまとめる「型」や「方向性」が先に定義されているのみです。
そして「3.入力情報」にて、初めて具体的な文章が登場します。僕が書いたプロンプトの大部分がこの部分に収まっています。
AIは、まず全体の構造を作り、後から「入力情報」をあてはめて(代入して)文章を書かせようというプロンプトを作りました。まるで数式のような構造で、普段プログラミングをしない僕のような人間にとって、この思考プロセスは非常に新鮮でした。
半端なプロンプトから始めてもいい:AIは思考のパートナー
さて、僕が力尽きてしまい途中で途切れてしまったプロンプトですが、AIから「AI利用の注意点」の項目として「著作権の問題」を追加してはどうかと提案してくれました。
確かに、以前Deep Researchを利用して作成したブログ記事では、僕が情報の真偽性や著作権の問題になるのではと感じ、必死にファクトチェックするということがありました。AIからアイデアをもらえたことで、止まっていた思考が再び動き出したのです。
このあと、僕は著作権と情報の真偽性(ハルシネーション)について体験談を交えた内容を追加して、ブログ記事執筆のプロンプトを完成させることができました。
最初から完璧なプロンプトを目指す必要はありません。考えが煮詰まってしまっても、まずは書けたところまでをAIに見せてみる。 このやりとりこそ、AIを思考のパートナーとして活用するコツなのだと気づきました。
人間として、できることとは何か?
AIが出力したプロンプトの中で、僕の書いた文章のほとんどは「入力情報」としてまとめられました。再度、見てみましょう。
- 【入力情報①】: 私の知り合いも、会社から「業務においてGeminiを使うように」と言われているらしいが「使い方がよくわからないし、なんとなく怖い」という理由から積極的に使えずにいる。
- 【入力情報②】: 機密情報や個人情報の入力→入力内容をAIへの学習データとして利用しない設定はできるものの、一時的にサーバーへ保存されるため、情報が削除される前に漏洩するというリスクがある。
- 【入力情報③】: ハルシネーションの発生→AIに関するニュースでよく目にするが、AIはもっともらしいウソをつくことがある。プロンプト時の参照情報をしっかりと入力したり、AIの出力を自分で確認したりすることが大事。
- 【入力情報④】: AIはスレッドの文脈からやりとりをする→AIとチャットを始めると、話題の内容によってチャットのスレッドが作成される。同じスレッド内でやりとりを続けると、AIに別の話題を振っても最初の話題を引き合いに出してきたりする。人間側からすると、AIが話題を動かしたくない頑固者のように見えてしまい、チャットをつまらなく感じてきてしまう。AIでプログラミングすると、同じエラーを発生するコードを繰り返し書かれてしまうため、プログラミング知識がないと具体的な指摘ができなくなってしまう。
- 【入力情報⑤】: よくも悪くも自分を肯定してくれる。
入力情報⑤に注目してください。急に文章が短くなって、なんとも味気ないと思いませんか?ここは僕がプロンプト入力で力尽きた部分です。
もちろん、入力情報が短かったとしても「記事の構成案」にて文章の方向性が決まっているので、記事を執筆することについて問題ありません。しかし、僕自身このことについて少し考えたことがあって、以前Xにこんなポストをしていました。
このポストを掘り下げて情報として入力していれば、自分にとって、さらに納得のいく記事に仕上がっていたはずです。
AIは、著作権に関する項目を補足してくれたように、「記事の構成案」は作り上げてくれました。しかし、構成の具体的な中身となる「入力情報」、特に僕自身の体験や感情、思考といった「生の情報」は作ってくれませんでした。もしAIがそれを作ったとしても、それはどこかから持ってきた情報を組み合わせただけの、「真実のように見える情報」に過ぎません。
記事の内容に深みを出すための「入力情報」、つまり自分の体験や感情や考え方は人間にしか作り出せないのです。
ブログ記事をビルに例えるなら、AIが作ってくれるのはビルの構造を支える「骨組み」や「設計図」であり、人間が作るのはビルの内側、空間に個性を与える「内装」や「インテリア」の部分です。どんなに見た目が立派な高層ビルでも、中身がただの打ちっぱなしのコンクリート空間だったら…とても寂しいですよね。
まとめ
今回は【初心者必見】「AIって、なんだか怖い…」が口ぐせのあなたへ。今日から使える5つの注意点と安全な使い方の執筆で利用したAIプロンプトに焦点をあてて考えてみました。
大きく3つの気づきを得ました。
- AIが作るプロンプトは、記事の方向性を示す情報が先に記述され、文章の個別具体的な情報は後に記述される。
- プロンプトは最初から完璧でなくていい。不完全でもAIに入力してみるのが大事。形式を整えてくれるし、追加情報も提案してくれる。AIからの出力をもとにして、最初のプロンプトを補足・修正していけば良い。
- 文章作成のプロンプトにおいて、AIは人間の考え方や体験を作り出すことができない。
どんなにAIが世の中を便利にしても、最終的に人の心を動かすのは、人間一人ひとりの「思い」や「体験」なのだと改めて感じます。これが抜け落ちた瞬間、途端に中身の薄い文章、あるいは恐ろしいフェイクが生まれてしまうかもしれません。
これからの時代に求められるのは、自分の考えや体験を、たとえ断片的な言葉でも、素直に文字にして表現していくことなのでしょう。
みなさんも、普段の生活で感じたちょっとした思いを言葉にして残してみませんか?
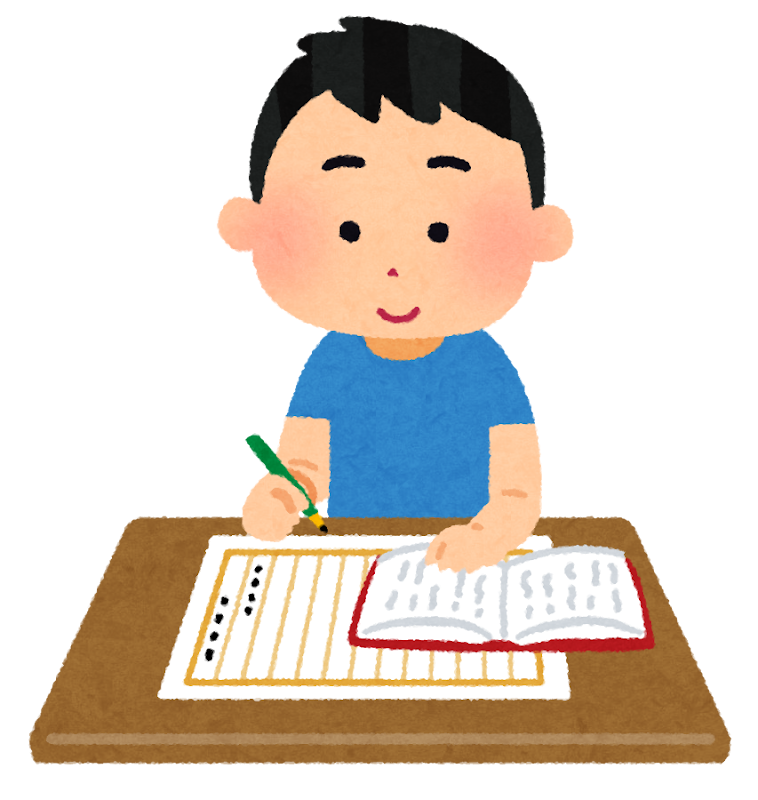
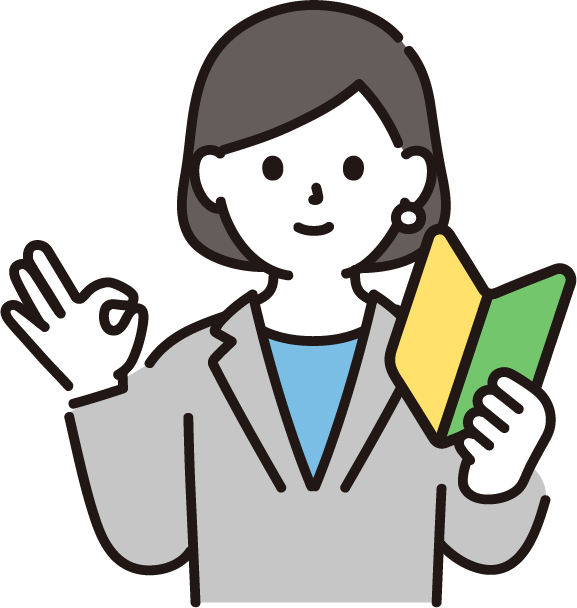

コメント