当ブログではAI執筆記事と、私自身の執筆記事を交互に投稿しています。
前回の投稿にて、AI執筆が10記事目となりました。
そして、この記事が私の10記事目です。続けている自分、えらい!
今回は、これまでAIで書いた記事を振り返り、AI執筆におけるメリットとデメリットをまとめます。
AI執筆、メリットとデメリット
AIを使った記事について、私が感じたメリットとデメリットは、それぞれ3つずつあります。
まずはメリット3つです。
- 圧倒的な構成の作成速度
- タイトルのアイデア出し
- メタディスクリプションの作成
次にデメリットを3つ挙げます。
- 情報は必ず自分で確かめる
- 体験談を含めてプロンプトを書くと、時間がかかる
- くどい文章になりがち
それでは、1つずつ見ていきましょう。
AI執筆、3つのメリット
1:圧倒的な構成の作成速度
圧倒的です。
思いのたけを書き出し、「このメモからブログ記事を作って」とAIに投げてしまえば良いんです。
自分で書いた内容を整理しようとすると、どうしても時間がかかってしまいます。
でも、AIなら一瞬です。
初めての投稿時、あまりにも簡単にブログ記事ができてしまい、私はショックを受けました。
もちろん、構成に納得いかないこともありえます。
ですので、私は記事作成の前に、「まず構成案を作って」とプロンプトして、構成を確認するようにしています。
最初に構成案に目を通しておくと、記事への納得感も高まります。
なんにせよ、AIはブログ記事の体裁を、何も言わなくても整えてくれます。
記事の形がハッキリするので、本当に便利です。
2:タイトルのアイデア出し
正直なところ、私はタイトルを作るのが苦手です。
もし作れたところで、適切なタイトルなのかどうか…不安だらけです。
でも、AIを使うと簡単にアイデアを出してくれます。
自分では思いつかないような、パワーワードも出してくれますので、タイトル作成への自信もわいてきます。
ただし、記事の中心となるキーワードが入ってない場合もありますので、自分で修正して使っていくのが良いです。
以下の記事は「ピアノ教室の探し方」についての記事ですが、タイトルから「教室の探し方」というキーワード抜けてしまいました。
3:メタディスクリプション等の作成、アイデア出し
メタディスクリプションとは、Webページの内容を要約した短い説明文のことです。
ブログ記事の要約です。AIの得意分野ですね。
「良いメタディスクリプション」には、要約だけではなく、記事のキーワードや文字数などなど、多くのポイントがあります。
AIはこれらのポイントを押さえながら、いい感じのメタディスクリプションを書いてくれます。
今のところ、当ブログのメタディスクリプションやタグなど、記事以外の部分は、AIにアイデアをもらっています。
私は記事を書きあげた直後だと、頭がパンク寸前で、何も考えられなくなってしまいます。
AIからアイデアをもらえて、本当に助かっています。
AI執筆、3つのデメリット
1:情報は必ず自分で確かめる
AIはウソをつく可能性があります。
AI活用時の常識として気をつけるべきです。
記事を書かせた場合も、AIが学習データやWeb上からの情報をもとにした内容があります。
細かい部分でも、情報の正確性は自分で確かめないといけません。
特にDeep Research機能は大変便利ですが、調査結果をそのまま記事として利用すると後悔します。
膨大なファクトチェック作業が発生するからです。
「あれ?AIを使ったはずなのに…作業が終わらない…」
こんなことにならないよう、自分の手のとどく範囲の情報を記事に載せましょう。
長岡花火に関するファクトチェックは、特に大変でした。もう、やりたくない…。
2:体験談のプロンプトは時間がかかる
AIで記事を作成する場合、自分の体験談はとても大事です。
体験談のないAI記事は、爆速で作成可能です。
でもその記事は、つまらない一般論か、ハルシネーションのウソ記事のどちらかです。
「体験談は、大事な一次情報」という言葉を、AI界隈ではよく見かけます。
全くもって、その通りです。
しかし、その体験や前提となる情報をAIに伝えようとすると…プロンプトの作成に相当な時間がかかります。
プロンプトさえ完成すれば、そこからの記事作成は早いです。
この作業、まるで料理みたいです。
調理そのものよりも、お肉や野菜を切るといった「下ごしらえ」に時間がかかる感覚です。
以下の記事も、良い点と注意点それぞれの体験をプロンプトで準備しました。
3:AIは、くどい文章を生成しがち
AIの文章では、「~ではありません。~なのです。」という強調表現をよく見かけます。
せっかちな私としては、結論を先に知りたいので、この表現を「くどい」と感じてしまいます。
また、AIは書き手の体験談から感情を読み取り、「情景が目に浮かぶようなストーリー」を提案してくることがよくあります。
このストーリーも、時として過剰に感じられます。
試しに、次の文を校正してもらいましょう。
初めて子どもとクッキー作りに挑戦。
ホットケーキミックスを使ったら、焼くときにクッキーが思いのほか膨らんでビックリしました。
でも、結果的においしいクッキーが作れて満足です。
「情景を豊か」にすると、次のようになります。
初めて子どもと一緒にクッキー作りに挑戦しました。
ホットケーキミックスを使ったら、焼いているうちにもくもくと膨らんで驚きました。
形は少し不格好になりましたが、親子で楽しめるおいしいクッキーができて大満足です。
私は、文字数の少ないスッキリとした記事を目指していますので、この表現は極力避けています。
自分の求める文章を書いてもらうため、プロンプトに「トーン&マナー」や「簡潔に記述して」等の注意点を書くことで、文章の形式や文字数を指定しましょう。
ちなみに、以下のような自分語りのテーマですと、情景豊かな方が良い感じのストーリーになります。
ただし、このような自分語り記事は、そもそも「読者にとって、あまり関心がない」という事実を留意するべきです。
最後は、必ず自分でチェック!
ここまで、AIを用いたブログ記事のメリットとデメリットをまとめてきました。
デメリットへの対策として、以下の3点を実行してAIに記事を書いてもらいましょう。
- 自分の調べられる範囲の情報を載せる
- 自分自身の体験をプロンプトへ書き込む手間を惜しまない
- きちんと求める文章の形式を指定する
これで記事の完成度は、かなり高いものになったはずです。
しかし、ここでもう一押し、最後に自分自身でチェックしましょう。
できあがった記事は本当に読みやすいのか?
同じことを何度も言っていないか?
情報は本当に正しいのか?
しっかり読んでみると、修正したい点がいくつも見つかるはずです。
ちょっとした部分だけでも、自分の言葉に置きかえてみましょう。
この「最後の仕上げ」の時間こそ、AI活用で生まれた時間なのです。有効に使っていきましょう。
私も引き続き、AIと共にブログ活動を続けていきます。
みなさんは、AIを活用の文章作成で、どのような点を注意していますか?
あなたが実践しているAI活用のコツや、失敗談があれば、コメントやXでのポストなどで、ぜひ聞かせてください。
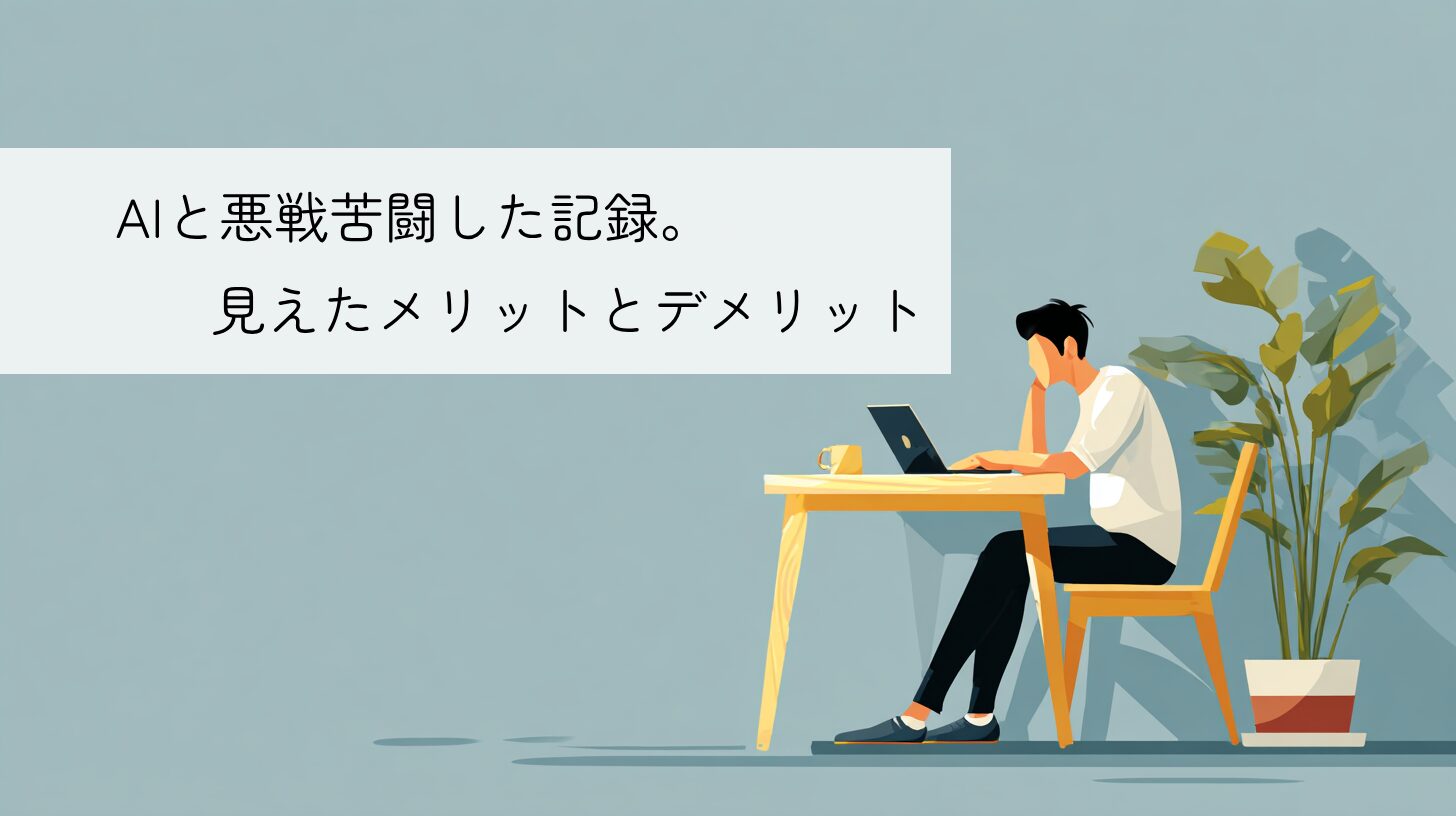
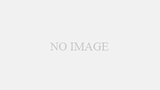





コメント