※この記事は、執筆者自身によるものです。【あんなに便利だったルンバを私が使わなくなってしまった5つの理由】に対する感想です。元の記事はこちら。
はじめに
ルンバは本当に便利で、長い間愛用してきました。しかし子供の食べこぼしを掃除機で吸い取るついでに、そのまま部屋全体を掃除してしまう…。んな毎日を繰り返すうちに、自然とルンバの出番はなくなっていきました。
それ以外にも、ルンバに対して少し気になる点が出てきたため、自分の考えを整理し、AIに記事の執筆を依頼してみることにしました。
まずは入力内容(プロンプト)
以下の内容をもとにブログ記事を書いてください。
テーマ「ルンバを使わなくなった理由」
ルンバを購入したのは7年前、最初は掃除機をかけなくても家をあらかた掃除してくれるのは本当に楽だった。特にそろそろ掃除機をかけなきゃ…という気持ちから解放されたのは大きかった。しかし今は使わなくなってしまった。その理由…
1 子どもが生まれ、ごはんの後パンくずやお米粒を掃除するために掃除機をかける機会が増えた
2 ルンバが入りこむと出てこれなくなる場所がある。風呂場や画像のようなソファの足元へルンバが入りこむと出てこれなくなる。ルンバの移動を制限する道具もあるものの、子どもの遊び道具になってしまいイチイチ回収して置き直すのも手間に感じる。
3 ルンバを起動するときは、家具を移動させてルンバが通りやすいような動線を確保しないといけない。
4 カーペットや畳が傷つき始めた
5 ルンバが部屋のすみずみまで完璧に掃除してくれるわけではなく、細かいところは結局掃除機になる
最後にルンバに適している環境とは…動線の確保が簡単でフローリングのお部屋。ルンバ自体はリモートで起動できたりして、とても便利なので是非とも使える環境を作っていきたい。
なかなかの文章量ですよね。ルンバへの思いを夢中で書き綴っていたら、プロンプトだけで一つの記事になりそうでしたので、概要が伝わるよう適度に省略してAIに入力しました。
また、今回は文章だけでなく、AIに生成させたソファの画像を添付して、状況を視覚的に伝えています。
AIは「煽りタイトル」がお得意
AIが生成した記事タイトルから見ていきましょう。
「あんなに便利だったルンバを私が使わなくなってしまった5つの理由」
ブログで読者の目を引くテクニックの一つに「タイトルに数字を入れる」というものがありますが、AIはそれをしっかりと押さえています。もっとも、これは私が理由に番号を振ってプロンプトを入力したからかもしれません。
また、「あんなに便利だったのに…使わなくなってしまった」という対比表現も、読者の「知りたい」という気持ちを掻き立てます。これも「ブログ記事を書く」というタスクのために、AIが意図的に選んだ表現なのでしょう。
伝わりにくい内容は「パワーワード」で解決
ルンバを使わなくなった理由の中には、状況を正確に伝えようとすると、どうしても説明が長くなってしまうものがあります。
2 ルンバが入りこむと出てこれなくなる場所がある。風呂場や画像のようなソファの足元へルンバが入りこむと出てこれなくなる。ルンバの移動を制限する道具もあるものの、子どもの遊び道具になってしまいイチイチ回収して置き直すのも手間に感じる。
この理由は説明が難しく、文字数を使ったうえで画像まで添付しています。特殊な形のソファの下から出てこないという部分は、私が実際にルンバを使っていて一番悩まされたものです。プロンプトも悩まされることになるとは…。
この複雑な状況に対し、AIは次のような見出しをつけました。
理由2:ルンバが迷子になる「魔の巣」の存在
「魔の巣」だそうです。思わず目が留まる強烈なワードです。この見出しだけで、中身が気になってしまいますよね。
ソファの形についての説明は…
座面の下部分が背もたれ側に向かって傾斜しているような形のソファ
と説明がされています。正直なところ文字だけでは、わかりづらい部分もあります。しかし、「魔の巣」のワードと画像のインパクトによって強烈なインパクトを感じます。
わかりにくい状況は、キャッチーなキーワードに置き換えることで、伝わりやすくしているんですね。
画像生成の難しさ
特殊な形のソファの画像をAIに生成してもらおうと思ったのですが、なかなか上手くいきません。
「座面の下部分が背もたれ側に向かって傾斜しているような形」という言葉を自分ではうまく説明できませんでした。そのため、オーソドックスな形のソファになってしまったり、脚のないタイプのソファになってしまったり、しまいには座面が脚から外れて宙に浮いたソファが生成されてしまいました。
画像生成は本来ならば、こんなイメージで~とか、何色を使って~とか、絵のタッチは水彩画風に~といった内容をプロンプトするものなのでしょう。しかし、ただのソファを表現するだけのプロンプトというのがわからず、試行錯誤を繰り返し、結局「座面の下が背もたれに向かってナナメ」ということで及第点の画像ができあがりました。

(実際の我が家のソファとは全く違う形なのですが、これは仕方ありません…)
AIにブログ執筆を依頼する前に、自力で画像生成に時間をかけてしまいましたが、AIが生成した記事の中に「座面の下部分が背もたれ側に向かって傾斜しているような形」という的確な表現があったので、記事を先に作ってもらい、その文章を元に画像を生成すればよかったと後から気づきました。
さらに言えば、「プロンプトが思いつかない」という悩み自体をAIに相談することもできます。画像生成に限らず、プロンプト作りが難しいと感じたら、それ自体をAIにお願いしてしまうのも一つの手だったと反省しています。
記事のメッセージは自分次第
この記事についての不満点、それは結論部分の締め方です。
ライフスタイルの変化で使わなくなってしまいましたが、いつかまた、ルンバが存分に走り回れるような環境を整えて、あの快適な「お掃除おまかせ生活」を取り戻したいと思っています。
ルンバについて色々と語ったにもかかわらず、最後は個人の感想で締めくくられています。せっかくのブログ記事なのに、読者へのメッセージがないのは非常にもったいないです。
しかし、これはAIの責任ではありません。私のプロンプトが原因です。
最後にルンバに適している環境とは…動線の確保が簡単でフローリングのお部屋。ルンバ自体はリモートで起動できたりして、とても便利なので是非とも使える環境を作っていきたい。
このように、私自身が感想文のような形でプロンプトを終えていました。ブログ執筆に不慣れなため、記事の締め方まで意識が回っていなかったようです。
最近知ったのですが、記事の締め方もプロンプト次第でコントロールできるのですね。例えば、
例えば…
・ルンバの購入を迷っている人の参考になるような記事を書いて
・ルンバの購入を勧めるような記事を書いて
・ルンバを使っている人たちから共感を得られるような記事を書いて
このように、「読者にどうなってほしいか」という着地点をプロンプトに含めることが重要なようです。結論部分には、書き手の思いを強く込めなければなりません。して、本当に伝えたいメッセージがあるなら、最後の一文くらいAI任せではなくて、自分で書いてしまっても良さそうですね。
まとめ
今回は【あんなに便利だったルンバを私が使わなくなってしまった5つの理由】を通して感じたことをまとめてみました。
- 読者の興味を引くタイトル作りがうまい
- 複雑な内容をキャッチーな言葉でまとめてくれる
- プロンプト作成自体もAIに手伝ってもらうという発想が大切
- 記事が伝えるメッセージは、書き手(プロンプト)次第
今回の経験から、今後のプロンプト作成における課題が見つかりました。それは、時にはプロンプト作成自体をAIに委ねてみること、そして、自分が発信したいメッセージの方向性をプロンプトにしっかりと盛り込むことです。
生成AIとのやりとりに行き詰まりや窮屈さを感じたら、そのままAIへぶつけてみると、新たな道が開けるかもしれませんね。
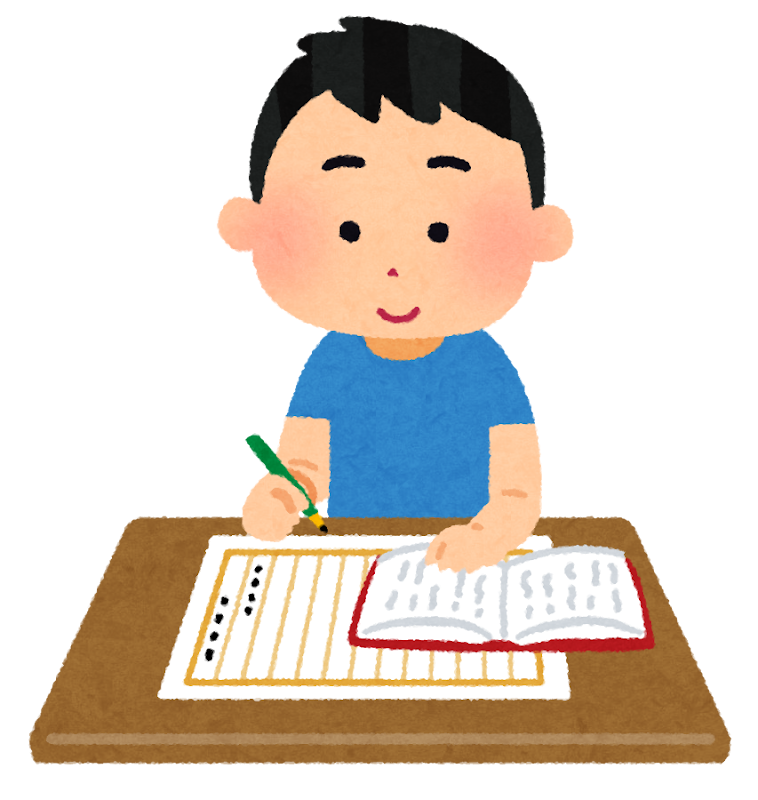


コメント