※この記事は、執筆者自身によるものです。【アマチュアオーケストラの「意外な」顔:100人規模の趣味を支える運営の舞台裏 】に対する感想です。元の記事はこちら。
はじめに
率直に驚きました。短時間で立派な記事が書けてしまうなんて、すごい。
私は以前、一記事だけブログを書いたことがあります。誰の目に留まらないような、簡単な自己紹介の記事だったはずなのに、どう書けばいいのかわかりませんでした。悩みに悩んで数時間、ようやく投稿へこぎ着けたというのに…。AIは私の要求を受け取るや否や、体裁の整った記事を出力してきました。あまりのスピード、そして表現の自然さ。初めて見たら呆気にとられるしかありません。
まずは入力内容(プロンプト)
私がAIへ入力したプロンプトを載せておきます。
アマチュアオーケストラの特性について紹介するブログ記事を書いてください。以下の点に言及してください。
- 趣味ではあるものの、オーケストラは100人規模の団体である。練習や本番の日程や会場、演奏する曲目、活動費の管理などしっかりとした運営組織が必要。
- 運営面は全て演奏者が担っている。
- 会社組織と同じような運営管理が必要だが、あくまでも趣味であるため、運営は無給で行われる。
- 自分はバイオリンを演奏したいという気持ちだけでオーケストラへ入団したが、パートリーダーを務めた時に運営業務が大変で面食らった。
- 自分は全てのアマチュアオーケストラを知っているわけではないが、一部の例外を除きほとんどの団体は同じような状況だろうという注釈をつける。
このプロンプトから出力された記事に表現の修正をお願いしたりして、合計3回ほど同じテーマで記事を書いてもらいました。
その後、私がそれぞれの記事から好きな表現を取り出して1つの記事にまとめました。
前書きに発見したもの
「どうやって書き始めればいいの?どうやって書き終わればいいの?」
ブログ記事や、夏休みの読書感想文など、何かを書くときに私が必ず感じることです。AIはどのように書き始めたのでしょうか?
アマチュアオーケストラと聞いて、皆さんはどんなイメージを抱くでしょうか?「音楽が好きで集まった一般の人たちが、仲間と心を一つにして壮大な音楽を奏でる」華やかで楽しそうな姿を思い浮かべる方が多いかもしれません。もちろん、それはアマチュアオーケストラの大きな魅力の一つです。
しかし、その華やかな舞台の裏側には、あまり知られていない「もう一つの顔」が存在します。
今回は、趣味で音楽を楽しむアマチュアオーケストラ(通称アマオケ)の、意外と大変な「運営」の側面について、私の体験談も交えながらご紹介します。
アマチュアオーケストラの「意外な」顔:100人規模の趣味を支える運営の舞台裏
なるほど、はじめに問いかけるんですね。「どんなイメージを抱くでしょうか?」とアマチュアオーケストラをあまり知らない読者へ呼びかけています。確かに多くのブログ記事で使われている表現です。
また、「オーケストラは華やかで楽しそう、だけど実は…」という内容になっています。きっと「アマチュアオーケストラを紹介するブログ記事」として執筆依頼したので、このような読む人を惹きつける表現を使ったのでしょう。
とにかく、書き始めの問いかけや「華やかで楽しそうな」オーケストラのイメージは私が入力していなかったものです。AIの考え出した内容が自然な形で文章に収まっています。まるで私自身に「最初からこう書こうと思っていましたよね?」と聞かれているようです。
おおまかな内容も、より具体的に出力してくれる
私がAIへ入力した部分の半分以上は、アマチュアオーケストラの運営面についての内容です。しかし、内容としては大まかなものでした。
再度、プロンプトの一部を載せておきます。
- 趣味ではあるものの、オーケストラは100人規模の団体である。練習や本番の日程や会場、演奏する曲目、活動費の管理などしっかりとした運営組織が必要。
- 運営面は全て演奏者が担っている。
- 会社組織と同じような運営管理が必要だが、あくまでも趣味であるため、運営は無給で行われる。
これに対してAIは、具体的な活動や役職を引き合いに出しながら記事を出力してくれました。
- 練習日程と会場の確保: 毎週の練習、そして本番のホール。100人規模の団体が活動できる場所を、数ヶ月先、時には1年以上前から確保する必要があります。
- 演奏曲目の決定: 在籍するメンバーから演奏したい曲目を募り、指揮者と相談しながら、演奏会のプログラムを決め、膨大な量の楽譜を手配・管理します。
- 会計管理: 団員から集める活動費(団費)や演奏会のチケット収入を管理し、会場費、楽譜代、謝礼などの支出をやりくりします。
- 広報活動: 演奏会を成功させるためには、ポスターやチラシの作成、SNSでの情報発信など、お客様に足を運んでもらうための広報活動も欠かせません。
団長、インスペクター(演奏現場の責任者)、ライブラリアン(楽譜係)、会計、広報など、様々な役職があり、団員は自分の楽器の練習と並行して、これらの運営業務を担っているのです。
特にインスペクターやライブラリアンは、オーケストラに特有の重要役職ですので、紹介されるとうれしいです。
それから「あくまでも趣味であるため、無給」という部分は「プロフェッショナル」という言葉に置き換えることで表現の工夫がされていますね。これもうれしいです。
仕事の合間や休日の時間を使って、団の運営のために奔走するメンバーの姿は、まさにプロフェッショナルです。彼らの献身的な努力がなければ、アマチュアオーケストラは決して成り立ちません。
1番驚いたのは「奇跡」というワード
今回のAIに執筆してもらった中で1番驚き、そしてうれしかったのは「奇跡」というワードです。
メンバー全員が「音楽が好き」という純粋な気持ちで集まっているからこそ成り立つ、ある種の「奇跡」とも言えるでしょう。
趣味でアマチュアオーケストラの活動をしている人たちは、演奏会を開催するという目的のために、演奏面そして運営面の両方で日々努力しています。そのような活動をできる人たちが今集まっていること、そして代々受け継がれてきたということ、そのことを私個人としては「アマチュアオーケストラを維持することは大変だけども、演奏活動の場を守り続けていることは素晴らしいな」と考えていました。
これまで自分が考えてきたことを一言でまとめると「奇跡」というワードがピッタリだと感じます。
私のプロンプトからAIが出力してきたアイデアの1つですが、とても満足のいく出力結果でした。
まとめ
AIからの出力は、ブログ記事を書いてくれという依頼を自然な形で達成できました。私が言及してくれと依頼した5つの点についても、抜けている情報を具体的に付けたし、わかりやすい言葉でまとめてくれます。
特に今回の記事では「プロフェッショナル」や「奇跡」というワードは、AIへのプロンプトを入力している段階で私が考えつかなかったものでした。しかし、記事で伝えたい内容に対してピッタリだと感じました。もしかしたらこれは、いろんな考えを次々出していくブレインストーミング的なアプローチを自分自身で行えたのかもしれません。
納得いくワードをAIから引き出せたときのハッとする感覚は、とても気持ちがよく、楽しい瞬間です。
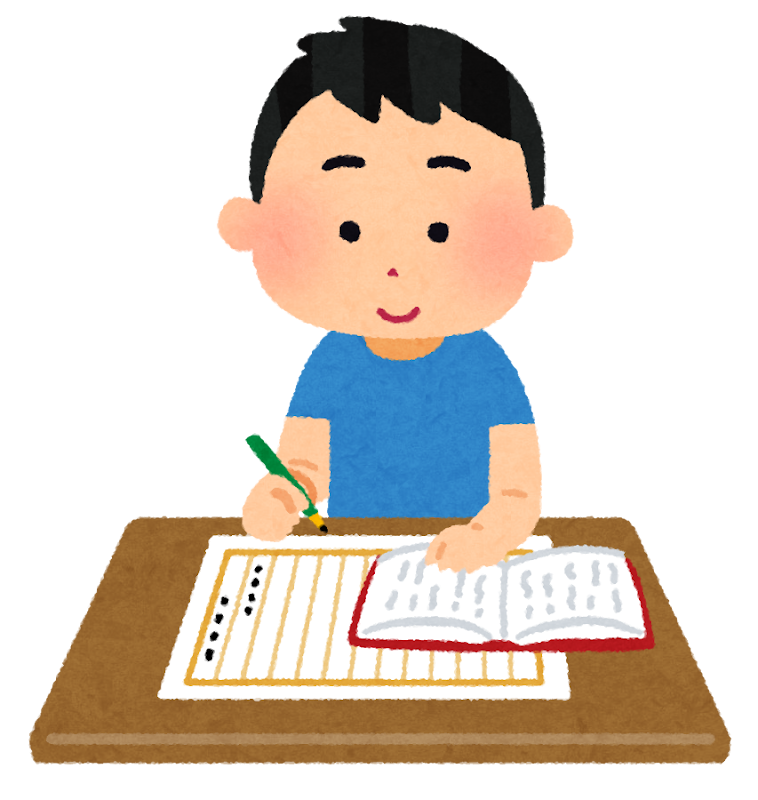
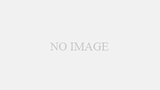

コメント