ピアノ教室って、どうやって探したらいいの?
お子さんの習いごとにピアノを、と考えたとき、無数にある教室を前になにから始めればいいのか、途方に暮れてしまうことはありませんか?
特に、私が住む東京のように選択肢が多い地域では、「グループレッスンと個人レッスン、どちらがいいのだろう?」「先生との相性はどうやって見極めれば…?」と、悩みは尽きないかもしれません。
実は何を隠そう、私自身がそうでした。4歳になる息子のためにピアノ教室を探し始めたはいいものの、情報が多すぎて完全に「ピアノ教室迷子」の状態に陥ってしまったのです。(2024年時点)
この記事では、そんな私が試行錯誤の末に、息子にとって最高の先生と出会うまでに経験した、リアルな道のりをすべてお話しします。
今、まさに教室探しでお悩みのあなた。この記事を読み終える頃には、ぼんやりとしていた教室探しの道のりがクリアになっていますよ!
最初の選択肢:グループレッスンはわが子に合うだろうか?
ピアノ教室を探すにあたり、私が最初に検討したのはグループレッスンの教室でした。
実は息子が3歳の頃、ヤマハ音楽教室のリトミックに親子で通っていた経験があります。そのため、音楽教室がどのようなものか、私自身ある程度のイメージを持っていました。
ヤマハのリトミック教室は、グループレッスン形式で進みます。
教室の中を思い出すと、そこには様々な子どもたちの姿がありました。先生のお話を真剣な眼差しでじっと聞いている子もいれば、途中で集中力が切れてしまい、お母さんお父さんの元へ駆け寄ってしまう子もいました。
その光景を見て、私は「グループレッスンには、子どもの性格によって向き不向きがあるのかもしれない」と感じたのです。ちなみに、わが子は後者の「集中力が切れてしまうタイプ」でした。
グループレッスンではお友達を作りやすい点が魅力です。一緒に音楽を楽しむ友達は、もしかすると一生の友達になるかもしれません。しかし、楽器とじっくり向き合うことを考えたとき、わが子には個人レッスンの方が合っているのではないか。そう考えた私は、次の選択肢を探すことにしたのでした。
ちなみに、ヤマハ音楽教室はグループレッスンだけでなく個人レッスンも実施しています。ピアノに限らず、楽器の教室を探す際、ヤマハ音楽教室はとても見つけやすくて良い教室です。気になった方はぜひ体験レッスンを申し込んでみてください。
次の挑戦:Googleマップで見つけた個人教室での“カルチャーショック”
グループレッスンではなく、個人レッスンで探そう。そう決めた私は、まずGoogleマップを開きました。手軽に探せるのが、インターネットの良いところです。
検索してみると、幸いにも近所で個人のホームページを持っている先生を見つけることができました。早速連絡を取り、見学へ伺うことになったのです。
先生にお話を伺うと、こちらの教室では「学校で音楽の授業についていけるようにする」ことを一つのテーマにしているとのことでした。
生徒さんの数にも驚きました。未就学児だけで50人、その他にも小中学生がたくさん通っており、土曜日は朝6時からレッスンをすることもあるそうです。なんでも、週末の部活動が始まる前に対応したレッスンの時間帯とのこと。
そのお話を聞いて、私はカルチャーショックを受けました。私のイメージでは、個人の音楽教室の先生が一人で受け持つ生徒数は、多くても全体で30人前後だと考えていたからです。
そして何より、私がピアノを習わせる目的との間に、少し距離があるように感じてしまいました。
私が息子にピアノを通じて得てほしいのは、演奏を通じて得られる、かけがえのない「体験」そのものです。
正しい姿勢を保つことで自分を律する力がつき、発表会で人前に立てば、本番独特の緊張感を味わえる。どんなに練習が苦しくても、自分の演奏が誰かに褒められた瞬間、今までの苦労が全て報われた気持ちになれる。
こうした経験のすべてが、子どもの人間的な成長に繋がるのではないか。私はそう信じています。
もちろん、先生の教育方針が悪いわけでは決してありません。ただ、個人のホームページを持つことでインターネット上で見つけられやすくなり、それだけ多くの生徒さんが集まっているのだなと感じました。
ピアノを習いたいというニーズの高さと、情報発信の大切さを改めて感じつつ、私はもう少し探してみようと決めたのでした。
迷走?出張レッスンという選択肢と、拭いきれない不安
個人教室という選択肢も一旦保留とし、私が次に関心を寄せたのは、先生が自宅まで来てくれる「出張レッスン」でした。
早速、一つのサービスに問い合わせて、希望の日付と時間帯を入力し、体験レッスンを申し込んでみました。後日、スケジュールが合う先生のプロフィールがメールで送られてきました。
その内容を読んで、私は再び衝撃を受けました。
どうやら、来てくださる予定の先生はバンド活動の経験がある方で、得意なジャンルは「J-POP」とのこと。私の頭の中では、ピアノの先生といえばクラシック(稀にジャズ)という固定観念があったのかもしれません。
しかし、少し考えてみれば、ピアノはどんなジャンルの音楽でも活躍できる楽器です。J-POPが得意な先生がいたって、何も不思議なことはないのです。実際、子どもたちにもポピュラー音楽は人気で、発表会で演奏する子もたくさんいます。
出張レッスンには、生徒側のスケジュールに合わせて柔軟にレッスンを設定できるというメリットがあります。ただ、私の心に一つの不安が浮かびました。出張レッスンの場合、スケジュールの都合上、毎回必ず同じ先生が来てくれるという保証はあるのだろうか、ということです。
もし、先生が変わるたびに音楽のジャンルまで変わってしまったら、息子も戸惑ってしまうかもしれない。そんな拭いきれない不安感から、結局、体験レッスンを受けることなく、この選択肢は見送ることになってしまいました。
最後の砦:専門サイト「ピティナ」で出会えた、理想の先生
いくつかの選択肢を検討しては、見送る。そんなことを繰り返していた私が、最後にたどり着いたのが「ピティナ(PTNA)・ピアノ教室紹介」という専門のサイトでした。
サイトの使い方はシンプルで、住んでいる地域を入力すれば、近所で登録されている先生を探し出すことができます。
検索結果を眺めていると、まるでSNSのプロフィールを次々と見ているような気分になりました。指導方針や経歴を詳細に書いている先生もいれば、ごく簡単な概要のみを掲載している先生もいる。正直なところ、情報が少ない先生に問い合わせるのは、少し勇気が必要だと感じました。
そんな中、家から自転車で10分ほどの距離に、先生がいることを見つけました。先生についての説明はとても簡素なものでしたが、思い切ってサイト経由で問い合わせてみると、まずはピティナ側からメールが届き、先生のお名前や連絡先を教えてもらえました。そこから、いよいよ先生ご本人に直接連絡を取り、体験レッスンのお願いをしました。
当日、実際にお会いした先生は、とても穏やかで素敵な方でした。
お話を聞くと、生徒さんの数は全体で30人ほどとのこと。私の抱いていた個人教室のイメージと近く、一人ひとりに目が届きやすい規模だと感じました。年に一度、2月頃に発表会を行っていることや、お月謝も納得のいく金額です。
そして何より、先生のお人柄に、私自身が「この先生なら、安心して息子を任せられる」と感じられたこと。息子もとてもリラックスした様子でした。
家に帰り、妻と「ぜひ、こちらの先生にお願いしよう」と話し合って、すぐに入会を決めました。後日、ピティナのサイトにも無事に先生が決まったこと、そして素晴らしい出会いの機会をいただいたことへのお礼を、メールでお伝えしました。
ピティナのサイトは紹介料もかからず、無料で利用できます。難点としましては、先生方の情報量に差があることと、サイトと先生の二方向へ連絡を取る手間があること、以上の2点が挙げられます。
しかし、ピアノの先生はSNS戦略の専門家ではありません。サイトの情報だけで判断するのではなく、実際に会ってみて、自分自身の目で確かめる。結局は、それが一番大切なのだと、この長い教室探しの旅を通じて、私は改めて感じさせられました。
わが家のピアノ教室探しの旅から見えた、8つのチェックポイント
さて、ここまで私の長いピアノ教室探しの旅にお付き合いいただき、ありがとうございました。
私が「ここは確認しておくと良いかもしれない」と感じたポイントを、8つのチェックリストにまとめてみました。
これから教室探しを始める方にとって、少しでも参考になれば幸いです。
1. グループレッスンか、個人レッスンか?
お子さんの様子を観察して、グループでお友達と一緒に学ぶのが良いか、個人でじっくり集中する方が良いのか、どちらの形式が合っているか考えてみましょう。
2. 生徒数はどれくらいか?
先生お一人で受け持つ生徒さんの人数も、判断材料の1つです。私の経験上、先生お一人で30人前後までが1つの目安だと感じています。進捗をしっかり把握してもらえたり、レッスン振替にも柔軟に対応してもらえたりできます。
3. レッスンの振替は可能か?
お子さんの急な発熱、親である私たちの仕事の都合、そして家族旅行などでレッスンをお休みする場合、振替が可能かどうか、事前に確認しておくと安心です。例えば、カルチャーセンターの教室などでは、曜日ごとに先生が変わるため振替が難しいケースもあるようです。
4. 親の同伴は可能か?
教室の方針によっては、レッスンの見学や同伴が認められないケースもあります。「ピアノ教室の時間は、子ども一人で頑張る時間」という考え方も、お子さんの成長につながると思います。ただ、もしご家庭での練習をサポートしたいとお考えなら、親もレッスンの進捗を把握できる同伴可能な教室が心強いです。
5. 発表会はあるのか?
発表会の有無も、ぜひ確認したいポイントです。人前で練習の成果を披露するという本番の経験は、日常生活ではなかなかできるものではありません。きっとお子さんにとって、貴重な経験となるはずです。開催時期や参加形式なども、合わせて聞いておきましょう。
6. ピアノはいつ頃購入するべきか?
もし、ご自宅にまだピアノがない場合、いつ頃までに準備すればよいか先生に相談してみることをお勧めします。焦って購入する必要はないかもしれませんし、先生の紹介で楽器店から割引を受けられるケースもあります。
7. お月謝はいくらか?
当然ながら、月々の費用は大切な確認事項です。教室によっては、お子さんの年齢やレベルが上がるにつれて、お月謝が変動する場合もあります。最初の体験レッスンの際に、料金体系についてもしっかりと確認しておきましょう。
8. 先生の人柄との相性はどうか?
これが最も大切なことです。子ども自身が「この先生、好きだな」と感じられるか。そして親である私たちも「この先生になら、安心して子どもを任せられる」と思えるか。体験レッスンは、その相性を確かめるための、何よりも貴重な機会です。
最後に、体験レッスンは有料の場合もありますので、その点も頭の片隅に入れておくと、よりスムーズに準備が進められると思います。
さあ、楽器を弾こう!あのワクワク感をあなたにも
ピアノ教室を探すという旅は、時に根気がいる、大変な道のりかもしれません。
たくさんの情報の中から、無数の選択肢をひとつずつ検討していく作業は、まるで終わりのない迷路に迷い込んでしまったかのような気持ちになります。
しかし、その道のりの先には、きっと素晴らしい出会いが待っていると、私は信じています。
良い先生との出会いは、子どもの可能性を大きく広げてくれます。そして、音楽と共に成長していく時間は、親子にとって大切な思い出になるはずです。
この記事が、あなたの、そしてお子さんにとって最高の先生と出会うための助けとなれたのなら。これから始まる音楽との日々に、楽器を弾くぞ!という、ワクワク感を感じていただけたのなら、とてもうれしいです。
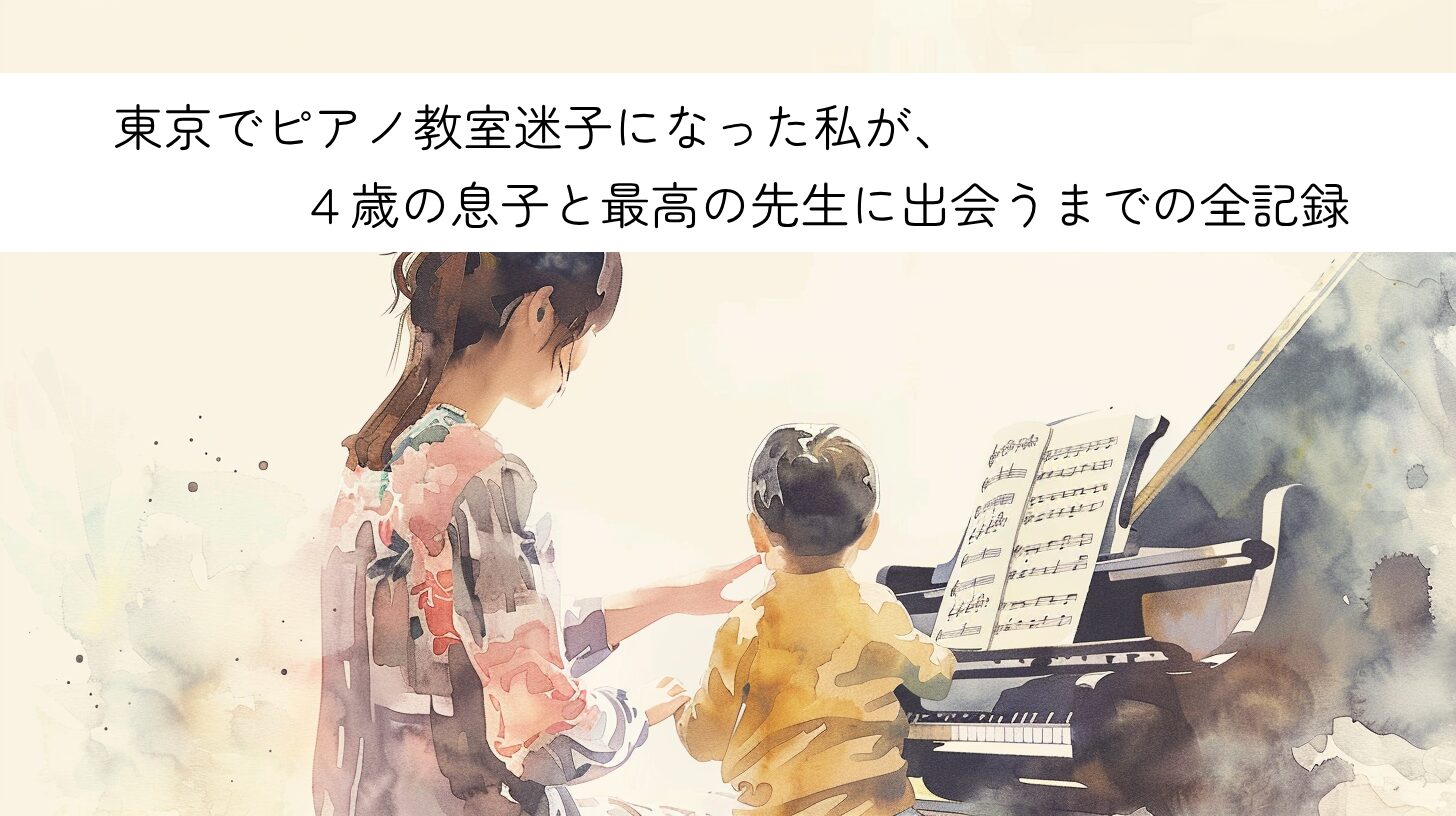


コメント