※この記事は、執筆者自身によるものです。【[購入前に必読]生ごみ処理機パリパリキューは本当に”買い”?2ヶ月使ったメリット・デメリットを徹底解説!】を作成した感想記事です。ぜひAI執筆の記事もこちらから読んでみてください。なお、AIはGemini Proを使用しています。
はじめに
みなさんはAIを使っていますか?
「毎日使っているよ。もうAIなしじゃ生きられない!」という人もいれば、「AIって一体なんなんだろう。よくわかりません!」という人もいると思います。
私はどちらかと言えば後者側の人間です。AIを使ってはいるものの、仕組みについての知識が少なく、AIのことはよくわかっていません。
当ブログでは、AIが執筆した記事と、それに対する私の感想記事を交互にアップしています。AIにブログ執筆を依頼すると「よくわからないけれど」非常に読みやすく質の高い記事を作ってくれます。
「なんて素晴らしい記事なんだ!すごいぞAI!すごいぞAIを使った自分!」とうれしくなる気持ちもある反面、「どうやって、この記事を書いたんだ…?」という、真っ暗な深淵を覗きこむような不安も感じます。
一体、AIは何を考えてブログ記事を出力しているのでしょう?
そんなとき、私の目に飛び込んできたワードが「Chain of Thought」です。今回は、AIに生ごみ乾燥機「パリパリキュー」についてのレビュー記事を執筆させる中でChain of Thoughtを実践した記録になります。
Chain of Thoughtとは?
AIに仕事(タスク)をこなさせる際に、最終的な答えだけでなく、その答えに至るまでの思考のプロセスを文章として生成させるプロンプト技術のことです。AIによる回答の精度向上や、思考プロセスの透明性を高めることができます。
実践の方法としては、プロンプトに「思考プロセスを明示して」や「一歩ずつ考えて」といった言葉を入力することになります。
結構、簡単そうですよね?早速やってみましょう!
何も考えずにChain of Thoughtを実践して大失敗
とりあえず「思考プロセスを明らかにしながら」と意図して入力してみたものが、こちらのプロンプトです。
生ごみ処理機「パリパリキュー(PPC-11)」を2ヶ月間使用したレビュー記事を、あなたの「思考のプロセス」を交えながら執筆してください。
(以下、記事の内容のため省略)
さあ、これでAIの思考がバッチリ見えるようになるはず…と思っていたのですが、実際に出てきたブログ記事は次のようなものでした。一部を抜粋して紹介します。
3. 【乾燥性能と運転音】夜動かせば朝にはパリパリ!気になる音は?
性能面も見ていきましょう。乾燥モードは2種類あります。
- パリパリモード(強力): 約9時間〜10時間
- ソフトモード(節電): 約4時間〜5時間
正直に告白すると、生ごみの種類(野菜くず中心か、水分が多いかなど)を判別してモードを切り替えるのが少し面倒で、結局いつも「パリパリモード」で運転しています(笑)。
(中略)
【シソタのホンネ✍️】リアルな使い方を伝える意味
製品の性能を語る時、つい専門用語やスペックを並べたくなります。でも、読者が本当に知りたいのは「自分の生活にどうフィットするか」のはず。そこで、2つのモードを紹介しつつも、結局は「パリパリモード」ばかり使っているという、ズボラで正直な実態をあえて伝えました。こうしたリアルな使い方は、レビューそのものの信頼性を高めてくれると信じています。
読んでみて、どのような印象を受けるでしょうか?
私はあまりの読みにくさに混乱してしまいました。
途中まで製品レビューについて読んでいると思ったら、急に「筆者の執筆意図の解説」が始まってしまい、ブログ記事として内容の一貫性が無くなっています。さらに、【シソタのホンネ】という自己主張強めのコーナー名、そして文末にくっついている(笑)の存在感から、ある種の可愛らしさすら感じます。
きっとプロンプトで「あなたの『思考プロセス』を交えながら執筆してください。」と入力してしまったことから、AIが私の気持ちをイメージし、その気持ちをアピールするように書いてしまったのでしょう。何も考えずにプロンプトしてしまいました。大失敗です。
とにかく、他にもChain of Thoughtを実践する方法を試してみます。
「Let’s think step by step」一歩ずつ考えてみよう
次は「一歩ずつ考えて」というワードを使ってみましょう。
「一歩ずつ考えて」というのは、Chain of Thought の手法について述べた論文「Large Language Models are Zero-Shot Reasoners」で提案されている「Let's think step by step」というワードを私が日本語訳したものとなります。「ステップバイステップで考えて」というワードも同義です。
思考のプロセスが執筆されないように、プロンプトの最初に入力した後、記事の具体的な内容としてパリパリキューについて言及してみました。
ブログ記事を一歩ずつ考えながら作成してください。
“””
生ごみ処理機「パリパリキュー(PPC-11)」を2か月ほど使ってみたレビューについて書く
(以下の内容は省略)
結果は前回と比べると、かなり変わりました。次の出力結果を見てみましょう。
生ごみ処理機「パリパリキュー(PPC-11)」のレビューブログ記事を、構成案から一緒に一歩ずつ作成していきましょう。
まずは、記事の骨子となる「構成案」を作成しました。 ご確認いただき、修正点や追加したい項目があれば遠慮なくお申し付けください。この構成で問題なければ、次に「タイトル」と「導入文」を作成します。
(以下、構成案は省略)
AIの提案する構成案を確認した後、こちらからゴーサインを出せば、次の作業ステップ「タイトル」「導入文」へ進むことができるようです。つまり、それぞれのパートで要点となるポイントを確認しながら執筆を進めていくという出力のスタイルになりました。ブログ記事作成についての思考プロセスを辿っていくことになりますので、とてもわかりやすいです。
執筆の都度、AIから確認が入るため、AIと人間が一緒に作業しているという感覚になります。項目ごとにどのように文章をまとめていくか説明が入るため、文章の構成を考えるのが苦手な私のような人間でも、安心して記事を執筆していくことができました。
試しに無料版のGemini Flashに対しても、同じようにプロンプトしてみたところ、同じような反応が返ってきました。無料版でも使えるのであれば、「一歩ずつ考えて」というワードを使えば、AIのバージョンに関係なく、安定してChain of Thoughtを実践できると言えそうです。
高度なテクニックを手軽に実現:魔法の言葉「一歩ずつ考えて」
Chain of Thoughtの実践方法がわかったところで、もう1度、失敗例のプロンプトを見てみましょう。
あなたの「思考のプロセス」を交えながら執筆してください。
改めてみてみると、確かに「執筆中の気持ちを表現しながら文章を書け」という指示になっています。もし、僕がこんな指示をされたら「えっ、どういうことですか?」と確認してしまいます。逆に言ってみれば、確認しないところがAIらしい、とも言えます。
当たり前の話ですが、「ブログ記事の執筆」と「執筆についての思考プロセスの説明」は別々のタスクです。同じプロンプトの中に複数のタスクが存在すると、タスク同士が混ざってしまい、出力結果に混乱を生じさせてしまう可能性があります。
もともと「ブログ記事の執筆」というタスクを指示していたプロンプトに、「執筆の思考プロセスを説明して」という別のタスクを追加してしまうと、AIは2つのタスクを混同してしまう可能性があります。そのため、Chain of Thoughtを使いこなすのは、実は高度なテクニックだったのです。
そして、そんなテクニックを手軽に実現させてしまう「一歩ずつ考えて」という言葉は、まさに魔法の言葉です。
まとめ:魔法の言葉でAIを「相棒」に
今回は、AIに思考プロセスを説明してもらう「Chain of Thought」を実践してみました。
- 失敗した方法:「思考のプロセスを交ぜて書いて」と曖昧に指示すると、記事本文と思考が混ざってしまい、読みにくい文章になる。
- 成功した方法: プロンプトの最初に「一歩ずつ考えて」と加えるだけで、AIは対話形式で構成案から本文まで、ステップごとに確認しながら進めてくれる。
- わかったこと: 「一歩ずつ考えて」は、AIに人間への確認を促す魔法の言葉だった。
試行錯誤するなかで、私は社会人として働き始めた頃に、よく言われた言葉を思い出しました。
「わからないなら、確認して」
今ではすっかり「確認すること」は私の習慣になり、聞き逃したことも「あとで確認すればいいや」なんて開き直って日々を過ごしています。(みなさんは、ちゃんと人の話を聞いておきましょう。)
AIは、人間から依頼されたら、複雑なことでも形にしようとしてくれます。しかし指示だけを受け取った状態で、作ってと言われたから作った成果物は必ずしも依頼の趣旨に応えるものではありません。このようなケースは人間社会でも、よくある光景です。
大切なのは、AIに人間へ確認をしてもらうことです。答えを出す前に「一歩ずつ考えて」もらい、人間とこまめに確認し合うことできれば、AIは最高の「相棒」になってくれるかもしれません。
気軽に始めたChain of Thoughtですが、最終的に社会人としての心構えを再認識させられるだなんて、思いもしませんでした。確認をいれることは物事を進めるうえで大事ですし、なにより安心感があります。
みなさんも魔法の言葉「一歩ずつ考えて」を使って、AIとの対話を楽しんでみてはいかがでしょう?
AIとの向き合い方に、新たな発見があるかもしれませんよ。
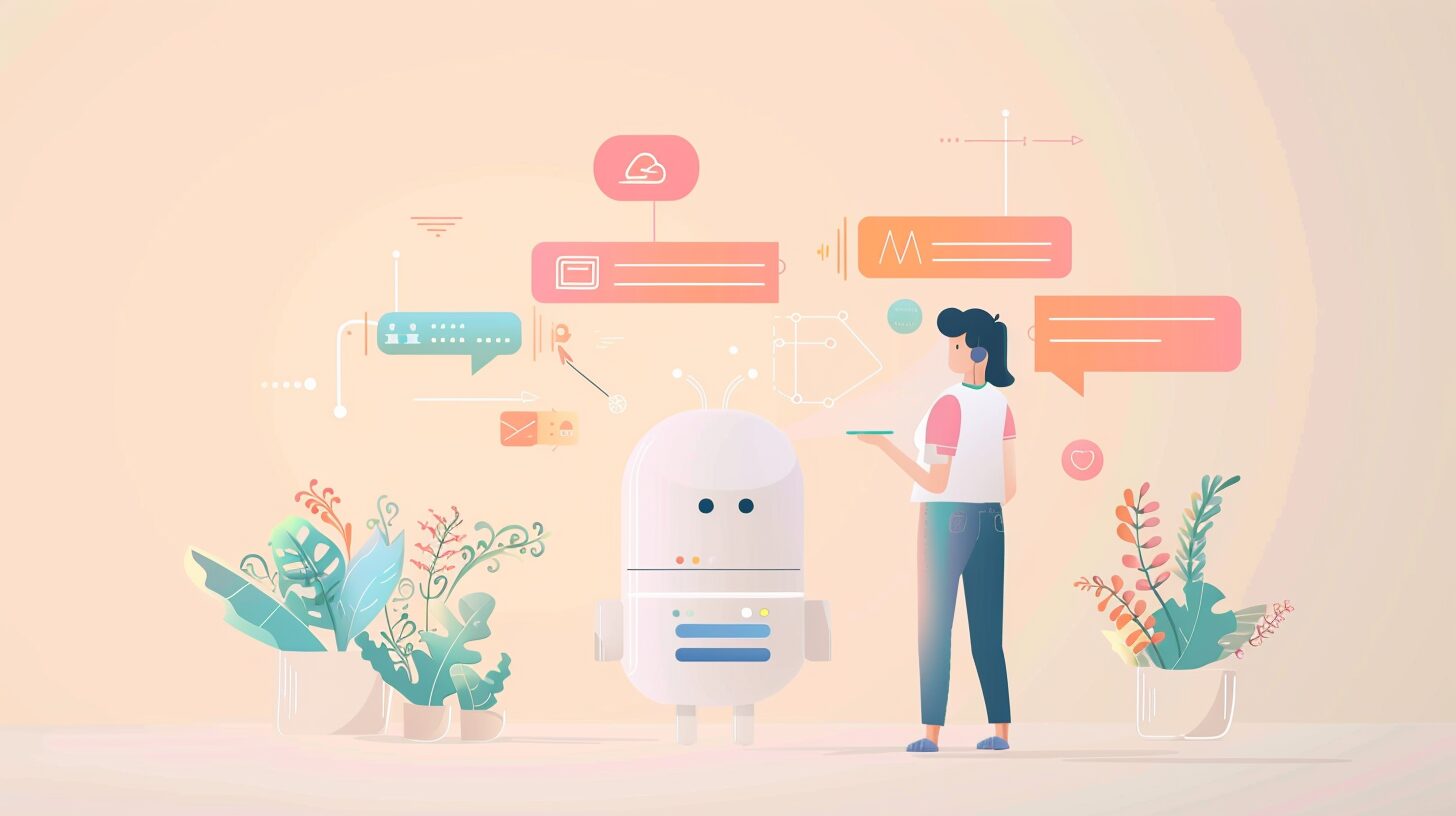


コメント