はじめに
「もう、やめたい…」
もし、あなたのお子さんが、今まで楽しそうに取り組んでいた習い事を、突然そう言い出したら?
「私のせい?」「もっと褒めてあげるべきだった?」
焦りと不安で、いっぱいになりますよね。
私は小さい頃からバイオリンを習ってきました。「習い事をやめたい」と思う気持ち、よくわかります。
この記事では
- 私がバイオリンを習ってきた体験談
- 650年以上も読み継がれる『風姿花伝』の教え
これら2点を通して、焦りを希望に変えるヒントをお伝えします。
この記事を読み終える頃には、お子さんへの関わり方が変わり、子育てが少しだけ楽になっているはずです。
バイオリン嫌いになった私を救った、先生の「魔法の質問」
小さい頃は、みんな喜んでくれた
きっかけは「親が憧れていたから」だそうです。
私は小さい頃からバイオリンを習ってきました。正直、練習は厳しかったです。
それでも、私は楽しく楽器を弾いていました。親戚の家へ遊びに行ったときに演奏をすると、みんなが「上手だね!」と笑顔で拍手してくれるのは、とてもうれしかったです。
誰かが喜んでくれる。シンプルな事実が、私の練習を支える大きなモチベーションでした。

練習が苦痛になった思春期の壁
しかし、小学校を卒業する頃になると、状況は一変します。周りの友達が、次々とピアノやバイオリンをやめていきました。
自分だけ、なぜ続けているのだろう?
そもそも、バイオリンは自分が「やりたい」と言って始めたものではありません。
運動部で汗を流す時間も、テレビゲームで遊ぶ時間も、もっと欲しい。
私自身、特にクラシック音楽へ興味があるわけではない。曲はどんどん難しくなるのに、以前のように褒めてもらえる機会は減っていく。
私の心は、すっかりバイオリンから離れていました。
先生の行動が、私と楽器を繋いだ
練習へのモチベーションが完全に消えかけていた、ある日のレッスン。先生は、こう尋ねました。
あなたは、どのくらいのレベルで楽器を弾いていきたい?
その問いに、私は正直に「趣味として、楽しめるレベルです」と答えました。すると先生は、次のレッスンから、練習内容をがらりと変えたのです。
難しい曲に挑戦するのではなく、来る日も来る日も、地道な基礎練習の繰り返し。この練習が、私のバイオリン人生を繋ぎとめてくれました。
基礎練習の日々が「楽しさ」をくれた
高校を卒業し、地元の先生のもとを離れてから、楽器に対しての気持ちは、いつの間にか前向きになっていました。
そして、私は基礎練習の大事さを痛感しました。
趣味で始めたアマチュアオーケストラ。そこでは、難しい曲を弾きこなす技術以上に、正確な音程やリズムといった基礎が、音楽を楽しむ土台になっていたのです。
今、私は心から演奏を楽しんでいます。先生は、私にとってバイオリンを「一生の友達」にしてくれました。

650年前の教えに学ぶ、伸び悩みの正体とは?『風姿花伝』の知恵
なぜ、『風姿花伝』が効くのか?
私の習い事の体験と、今あなたのお子さんが直面しているカベ。そこには共通点があります。
それを教えてくれるのが、室町時代の能役者、世阿弥(ぜあみ)が残した『風姿花伝』です。
これは単なる能の理論書ではありません。
一つの道を極める中で、人がどう成長し、どんな壁にぶつかるかを描いた、普遍的な「人の成長の指南書」です。
成長は予測不能?年齢別の育て方「七歳」「十二、三より」
年齢に応じた稽古の心構えが記されています。これを現代の習い事に当てはめてみましょう。
まず「七歳」(習い事を始めたての頃)です。
とにかく楽しくやらせることが大切。難しい理屈は、飽きてしまうだけです。
次が「十二、三歳」(小学校〜中学生)です。
心と体が大きく変化し、スランプに陥りやすい頃。とにかく基礎を磨くことが大切。
スランプの答え :「時分の花」と「まことの花」
なぜスランプに陥るのでしょう。その答えが「時分の花(じぶんのはな)」と「まことの花」にあります。
「時分の花」
若さや珍しさから生まれる、一時的な魅力のこと。
幼い頃によく褒められたのは、「時分の花」が咲いていたからです。しかし、これは年齢とともに必ず枯れてしまいます。
「まことの花」
厳しい稽古の末に手に入れた本物の実力。
生涯枯れることのない、その人だけの魅力です。
お子さんの「やめたい」は、「時分の花」がしぼみ、「まことの花」を咲かせる、産みの苦しみのサインなのです。

親の焦りを希望へ:3つのアクション
『風姿花伝』は、親の役割が「教える」だけではないと教えてくれます。具体的にどうすれば良いか、今すぐできる3つのアクションを提案します。
親は「最高の観客」であること
子供が「やめたい」と言う原因は、決して親のせいだけではありません。次のステージへ進もうとしているのです。
私たち親ができるのは、子供の成長を信じて、静かに待つこと。
いつか必ず「まことの花」が咲く。親はその日を心待ちにする「最高の観客」になりましょう。子供は、人生という大舞台の主役なのです。

「昨日の我が子」と比べる
周りの子と比べて焦ってしまう。痛いほど分かります。しかし、四季それぞれに違う花が咲くように、子供の成長のペースも一人ひとり違います。
比べるべき相手は、「昨日の我が子」です。
一音でも多く弾けた、少しだけ姿勢が良くなった、昨日よりできるようになったことを見つけましょう。
小さな成長を見つけて、言葉で伝えてあげてください。その積み重ねが、子供の自信に繋がります。
「小さなゴール」を決める
練習へのやる気を引き出すには、子供の自主性を尊重することが効果的です。
小さなゴールを決めてみましょう。
「1分間だけ背筋をピンと伸ばす」といった、簡単な目標を1つだけ提案してみましょう。
練習時間を短くしても、達成感を得られれば、子供の心は習い事から離れません。
まとめ:子供の「やめたい」は、成長のサイン
子供からの「やめたい」は、親の心を大きく揺さぶります。しかし、それは決してあなたの育て方が間違っていたということではありません。
『風姿花伝』が650年以上も前から教えてくれているように、子供が今だけの魅力「時分の花」から、本物の実力「まことの花」へ、成長しようとしているサインなのです。
私の経験も、まさにそうでした。
親として、できることは次の3つです。
- 成長を信じて待つ
- 「昨日のわが子」と比べる
- 小さなゴールを決める
焦る気持ちをこらえ、子供の人生の「最高の観客」になってみませんか。小さな成長を見つけて、一緒に喜んであげてください。
まずは1週間、お子さんを静かに見守ることから始めてみてはいかがでしょうか。
今、あなたがぶつかっている壁は、親子の絆をより一層深めるための素晴らしい機会になるはずです。
参考文献
- 世阿弥 (著), 水野 聡 (訳) (2005). 『現代語訳 風姿花伝』. PHP研究所.
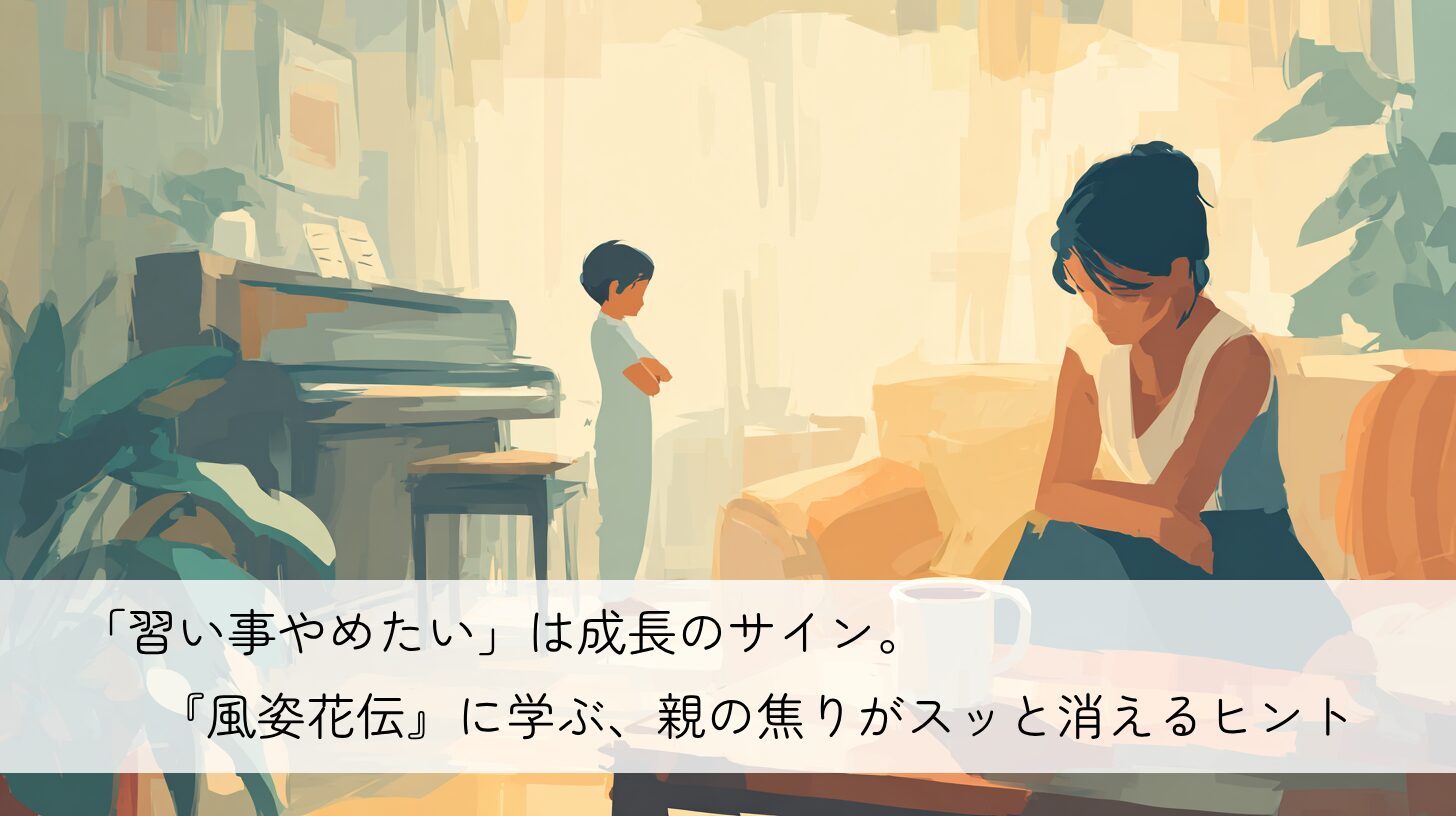


コメント